まちプラあきた中央のHPをご覧いただきありがとうございます。
今回紹介させていただくのは、川尻新川町にある出入役所跡です。
この出入役所があった場所には、今、民家が建っています。出入役所の建物はそれはそれは立派で、ある時代には藩主の遊覧所にも利用されていたと言われています。見てみたかったですね、、、。
出入役所は、関所や番所と同じものです。寛文8年(1668年)川尻新川町(旧新渡町)に建てられ、酒田街道から旧藩の領内に入る旅人、船の荷物などを調べていました。
豪商(大資本を持ち、規模の大きな商売を営む商人のこと)長谷川勘兵衛さんという方が建てて藩に献上したものだといいます。
出入役所は建ってから200年ほどで、慶応元年(1865年)に川口新町(現旭南3丁目)に移され、俗に「川口お役所」と呼ばれるようになりました。
慶応4年(1869年)、戊辰戦争で藩主が川尻村まで出陣し、本陣を出入役所のところにおいたそうです。戦況がおもわしくなくなり、前回説明した一乗院のところにうつったところまではわかっています。
【川尻】佐竹氏の祈願寺
この戦争の時、兵士は川尻村の農家に宿営(軍隊が兵営外で宿泊すること)し、食糧はすべて養蚕家の人たちが主となって炊き出したといいます。川尻で養蚕が行われていたことについてはこちらの記事をご覧ください。
【川尻】川尻組とは?
最後まで読んでいただきありがとうございました。
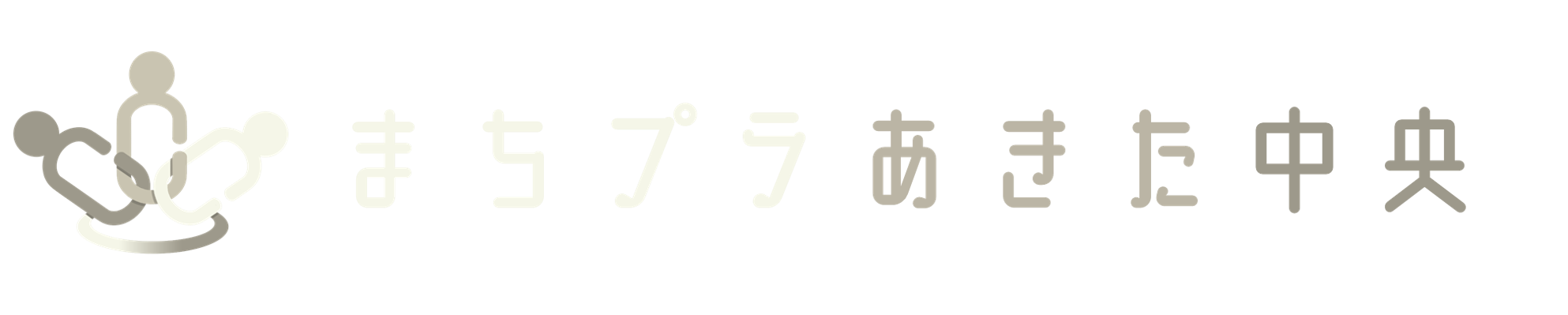



川尻って歴史が深そうですね。探検してみたくなりました。