みなさまこんにちは!!☀️
今回は改めて、寺内 という地域について、いったいどんな地域なのかをおさらいしていきたいと思います!!
今回を機に、
過去の投稿を見返したり、
これからの投稿をご覧になったりしていただけるとうれしいです!!!
寺内地区は場所にすると、
県庁や市役所などのある市街地と、
港町として栄えた歴史のある土崎地区との
中間にあります!!
〈地名の由来〉
その昔、東門院をはじめ、
妙覚寺、光明寺、大悲寺 といった寺々の内側にあったことが由来??
起伏の多さが特徴の地形から、
小高い丘陵地で清水の湧く所
という意味で、
「高清水の丘」
とも呼ばれています!
〈豊かな水と緑〉
古くから枯れることなく湧き続ける高清水霊泉
木々に囲まれて神秘的な雰囲気を帯びる空素沼
地域の人たちの生活を見守り続ける市内最古の巨木、旭さし木

〈歴史の宝庫)
現在も発掘調査の続く秋田城跡
長い歴史で地元の人々の守護神、古四王神社
紀行家といしても名高い菅江真澄のお墓
毎年5月7日、8日の二日間
このお祭りが行われます!!
〈祭りの流れ〉
①神様を迎えた神輿が町内を廻る。
②途中、御旅所という近くの昼寝山で、いったん休憩。
③巫女神楽などの祭祀を行う。
④神職や氏子たちに守られながらさらに町内を練り歩く。
〈見所〉
・氏子のもつ丈の長い糊付棒(長さ3m・太さ9cmの杉の棒に、水に溶いた米の粉を塗りつけたモノ。この米粉の粘りや落ち方で豊凶を占う)が目を引く!!
・行列が奏でるゆったりとした太鼓のリズムと、「ヤンヨーヤンヨー」という独特のかけ声

奈良時代から平安時代に渡って、当時の出羽国に置かれた
大規模な地方官庁の遺跡!!!
古代の政治・軍事・文化の中心地!!!
天平5年に、出羽柵が「秋田村高清水岡」に移されて、
天平宝字4年頃に、阿支太城(秋田城)と呼ばれるようになりました!!!
奈良時代には、出羽国の政治を行う、「国府」 が置かれ、
それ以北の国や大陸との
外交や交易の拠点 として重要な役割を果たしていた!!
昭和14年には
国の史跡に指定されました!!!

今後は、今回紹介したなかでまだ深掘りできていない場所を紹介したり、
現代的なトピックも紹介したり
できたらと思っています!
乞うご期待ください!!!
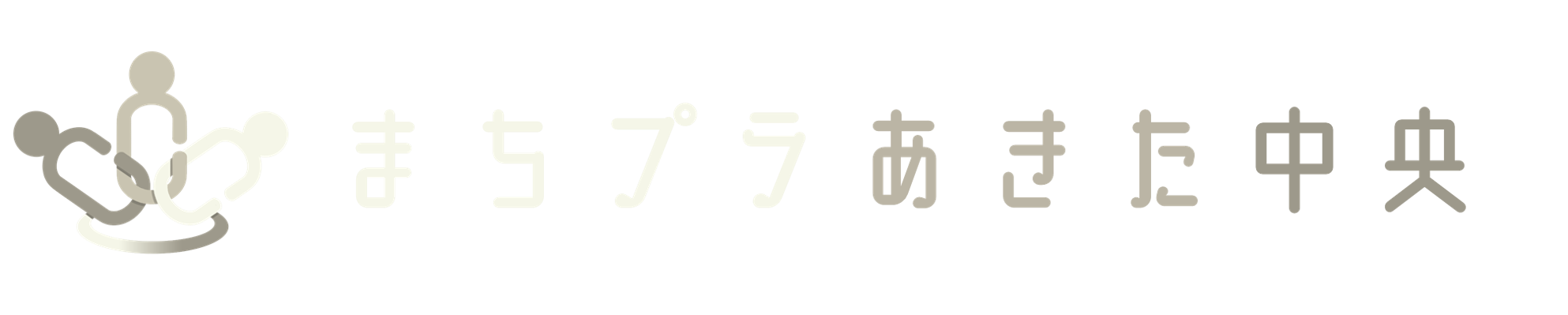



コメントを残す